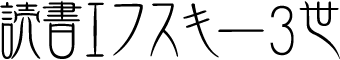- 著者:ポール・オースター
- 翻訳者:柴田元幸
- 出版社:白水社
- 作品刊行日:1987/04/20
- 出版年月日:1999/06/30
- ページ数:228
- ISBN-10:4560071314
最後の物たちの国でというポール・オースターの5番目の小説を読みました。この小説はポール・オースターを有名作家にしたニューヨーク三部作と世間で一番読まれているムーンパレスのちょうど間に発表された作品です。
ポール・オースターの代名詞とも言えるニューヨークを舞台にした作品ではなく、主人公も初めて女性である事、手紙形式の文章などなど今までのポール・オースターとは違いすぎて、本国アメリカでは他の作品に較べて比較的に受け入れられなかったようです。
だがしかし!日本の読者にはこの作品をポール・オースターの一番と言っている方も多いらしい。そして読んで納得。あまりに作風が違いすぎて「これは本当にポール・オースターが書いたものなのか!?」とビックリしましたが、たしかにこれは面白い。
世界の破滅を描いた物語。
これが1987年の作品だと言うのだから驚きです。ポール・オースターの描く世界の破滅は、他の作者とはちょっと違う。ということで、最後の物たちの国でのレビューに入っていくことにしましょう。
スポンサードリンク
小説『最後の物たちの国で』 – ポール・オースター・あらすじ
読書エフスキー3世 -最後の物たちの国で篇-

あらすじ
書生は困っていた。「話が最初に戻っている!」と仕事中に寝言を言ったせいで、独り、無料読書案内所の管理を任されてしまったのだ。すべての本を読むには彼の人生はあまりに短すぎた。『最後の物たちの国で』のおすすめや解説をお願いされ、あたふたする書生。そんな彼の元に22世紀からやってきたという文豪型レビューロボ・読書エフスキー3世が現れたのだが…
最後の物たちの国で -内容紹介-



これらは最後の物たちです、と彼女は書いていた。一つまた一つとそれらは消えていき、二度と戻ってきません。私が見た物たち、いまはない物たちのことを、あなたに伝えることはできます。でももうその時間もなさそうです。何もかもがあまりに速く起こっていて、とてもついて行けないのです。
引用:『最後の物たちの国で』ポール・オースター著, 柴田元幸翻訳(白水社)







最後の物たちの国で -解説-











































































































批評を終えて











いつもより少しだけ自信を持って『最後の物たちの国で』の読書案内をしている書生。彼のポケットには「読書エフスキーより」と書かれたカセットテープが入っていたのでした。果たして文豪型レビューロボ読書エフスキー3世は本当にいたのか。そもそも未来のロボが、なぜカセットテープというレトロなものを…。


名言や気に入った表現の引用


この街に住んでいると、何ごとも当然とは受け取らなくなります。一瞬目を閉じたり、うしろを向いて別の物を見ただけで、たったいま目の前にあった物がもうなくなっているのです。何ものも続きはしません。そう、心のなかの思いさえも。それを探して時間を無駄にしてはいけません。いったんなくなった物は、もうそれでおしまいなのです。
pp.5-6
食べたいという欲求がなかったら、絶対にやって行けないことは確かです。でもここでは何ごとも最低限で済ませることに慣れなくてはなりません。欲しがる気持ちが弱まれば、より少ないもので満足するようになります。必要とするものが減れば減るほど楽になるのです。この街にいると誰でもそうなってきます。さまざまな思いを、街はひっくり返してしまいます。人を生きたいという気持ちにさせておきながら、それと同時に、人生を奪い去ろうとするのです。逃げるすべはありません。何をするか、しないか、どちらかしかありません。何かをしたとしても、つぎにもう一度できる保証はありません。しなかったなら、もう二度とすることはないでしょう。
p.7
望みが消えてしまうとき、望みというものの可能性さえ望まなくなってしまったことに気づくとき、人は何とかして進みつづけようと、夢や子供っぽい思いや物語で空っぽの空間を満たそうとするものなのです。
p.14
人々がいつも決まって嘘をつくというのではありません。ただ、過去に関する限り、真実は往々にしてあっという間にぼやけてしまうのです。ほんの数時間のうちにいくつもの伝説が生まれて、尾ひれのついて話が流通し、事実は見る見るうちに、無数の途方もない仮説の山に埋もれてしまう。この街で採るべき最良の方策は、自分の目で見たものだけを信じることです。でもそれさえも絶対に確実ではありません。なぜなら、物事が見かけどおりということは元々ほとんどないのだし、ここではなおさらそうだからです。一歩歩むごとに吸収すべき要素はおそろしく多く、理解を絶する事物も数限りなくあります。あなたが何を目にするにせよ、それはあなたを傷つける可能性を秘めています。あなたという人間を減少させてしまう力を宿しています。まるで、単に物を一つ見ることによって、あなたという人間の一部があなたから奪われてしまうかのように。物を見るのは危険な行為だと身をもって感じることもしばしばです。
p.24
私の努力とはほとんど無関係に、言葉はやって来ます。考えても考えても言葉が出てこない、もうどうあがいても絶対に見つかりっこない、そう思ったところではじめて言葉はやって来るのです。毎日が同じ苦闘、同じ空白のくり返しです。忘れたいという欲求、そして忘れたくないという欲求のくり返し。それがはじまったら、この地点、このぎりぎりの地点まで来てやっと、鉛筆が動き出すのです。
p.47
本当に、物の見方なんてあっという間に変わってしまうものです。この街へ来る前に、もしも誰かに、あなたはやがてここに住むことになるんですよなどと言われたら、私は絶対に信じなかったでしょう。でもいまは至福の思いでした。何かとてつもない贈り物をもらったような気分でした。不潔とか、安楽とかいった概念は、結局のところ相対的なものにすぎません。
p.63
あなたはそう思わないかもしれないけれど、物事は反転可能なものではありません。入れるからといって、出られるとは限りません。入口は出口にならないし、たったいま通貨してきたドアがもう一度ふり返ったときもまだそこにあるという保証はありません。それがこの街の掟なのです。ある質問に対する答えがわかったと思った瞬間、質問そのものが意味をなさないことを思い知らされるのです。
p.104
本より大切なものはたくさんあります。祈りより食べ物が先です
p.116
向こうに何があるのか知らなければ決してドアをノックしてはならない
p.119
美人はお医者になっちゃいけないのよ。ルール違反よ
p.152
人生には、誰も強いられるべきでない決断があります。とにかく精神に対してあまりに大きな重荷を課してしまう選択がこの世にはあると思うのです。どの道を選ぶにせよ、結局絶対に後悔することになるのであり、生きているかぎりずっと後悔しつづけるしかないのです。
pp.162-163
私たちはみな、いろんな物事を当たり前のものとして受け止めています。しかもそれが、食べ物、寝ぐらといった、おそらくは私たちの生得権に属する事物となると、それらを自分自身の本質的要素と考えてしまうようになるのに、さして時間はかからないのでしょう。いままで持っていた物を失ってはじめて、私たちはその物の存在に気づきます。そしてそれをふたたび取り戻すやいなや、またしてもその存在を気に留めなくなってしまうのです。
p.168
それはどれもみな違った物語でしたが、同時につきつめればどれもみな同じ物語でした。数珠つなぎの不運、もろもろの誤算、じわじわとのしかかってくる状況の重圧。我々の人生とは、要するに無数の偶発的出来事の総和にすぎません。それらの出来事が細部においてどれほど多種多様に見えようとも、全体の構成がまったき無根拠に貫かれているという点においてはみな共通しているのです。
p.171
これはお芝居よ。嘘というのは自分が得をするためにつくものだけど、私たちは何の得もしないわ。他人のため、他人に希望を与えるためにやるのよ。
p.196
できなきゃできないだけのことよ。でもできるかできないか、やってみなくちゃわからないでしょう?
p.197

最後の物たちの国でを読みながら浮かんだ作品


レビューまとめ

ども。読書エフスキー3世の中の人、野口明人です。
ニューヨーク三部作を読み終えて、次に読んだ作品が『最後の物たちの国で』だったので、そのあまりの作風の違いに度肝を抜かれました。
マジでこれ、ポール・オースターなの!?と何度か背表紙を確認してしまいましたよ。
本当に色々なものが書けるんですねぇ。小説家さんってすごい。ってか、ポール・オースターってすごい!
それにしても今回はディストピア小説だったわけですが、今まで読んできたディストピア小説とは一味違った内容で、そこからもポール・オースターらしさがにじみ出ているのかなぁ〜と思います。前衛的な作家といわれるのもよく分かる。
おそらく純粋なディストピア小説を読みたいのであれば、他の作品の方が純度が高いでしょう。危機的状況を突き詰めていたり、狂気や緊張感が伝わってくる作品を求めているのなら『最後の物たちの国で』じゃなくて良いのです。
『最後の物たちの国で』は、もっと現代的でマイルドな読み心地なのです。もちろん読むのが辛く、心が痛くなる描写とかもあるっちゃあるんですけどね。それでも他の作品よりもマイルドです。
例えばお化け屋敷にただただ怖さを求めて入りたい人もいるでしょう。しかし、怖さは弱くともその世界観が好きだから入りたいという人もいるじゃないですか。
この小説はどっちかというと後者の方への小説なのだと僕は思います。ディストピアが生み出す危機感や緊張感よりも、この作品が生み出す「なんか現代でもこの状況あり得るんじゃないか!?」っていう世界観、ある意味でリアリズム寄りのディストピアを描いている作品。
まさに「そこにあるかもしれない世界」を描いた作品だと思うのです。
ちなみに、今回の作品は手紙形式でして、一体誰に向けて書いたのか?って所が気になってたんですよ。そこでここからは読書エフスキーの延長戦という事で、レビューの続きを書いてみました。
興味がある方だけお読み下さいませ。
- 延長戦を表示
最後の物たちの国で -レビュー延長戦-

書生 先生、このブログ初の延長戦だそうですよ。
読書エフスキー3世 エ!?マダナニカ話スンデスカ?
書生 はいはい。ポチッと。
読書エフスキー3世 ゴゴゴゴゴ…。
書生 ところでさっき、話が途中で終わっちゃったじゃないですか。やっぱりハッピーエンドかどうか知りたいんっすけど。
読書エフスキー3世 うーむ。ハッピーエンド…と言えますかね。とりあえず読んでいて後味の悪いものではありませんでしたね。
書生 お、後味悪くないんですね!
読書エフスキー3世 なんというか、アンナが魅力的だったってのも大いに関係するとは思うんですけど、生きていく強さみたいなのを感じ取れるんですよね。
書生 あんなに過酷な国なのに、それに負けない前向きさみたいな?
読書エフスキー3世 ある意味で手紙は読者に向けて書かれたとも言えると思うんですよ。写真の男っていたでしょう?
書生 ええ。アンナのお兄さんの後に出版社から調査に来た男ですよね。
読書エフスキー3世 その男がサムって言うんですけどね、彼の仕事はこの国の惨状を記録して、外の世界に知らしめることだったんですよ。
書生 ほほう。
読書エフスキー3世 この作品の中では、サムが書いていた記録は消失しちゃうんです。
書生 さすが最後の物たちの国。そこにあったのに、次の瞬間にはもうすでになくなっているんですもんね。
読書エフスキー3世 んでね、サムとアンナは作中の中で恋人同士なんですよ。
書生 旅行先で自分の国の人を発見したら、なんか知らんけど親密になるパターンのやつですね!
読書エフスキー3世 それでまぁ、サムの仕事がオジャンになっちゃったわけじゃないですか。
書生 ええ。
読書エフスキー3世 それでまぁ、アンナはきっとそういうつもりはなかったのかもしれませんけど、結果的にはサムに変わって、最後の物たちの国の惨状を外の世界に届ける事になったんじゃないかなって。
書生 外の世界には届いたんですか?
読書エフスキー3世 届いているじゃないですか。
書生 へ?
読書エフスキー3世 私達、読者ですよ。私達がこの作品を読む時、最後の物たちの国の出来事を詳細に知ることができるでしょう?それはこの手紙のおかげでしょう?
書生 あら。これはポール・オースターお得意のメタなんちゃらってやつなんじゃないですか!?
読書エフスキー3世 作品と現実の境界線を曖昧にして、ディストピアの世界を現実の世界の事のように感じさせる。私達は最後の物たちの国に対して何が出来るだろうか。…なんて事を考えさせる。
書生 ふむ。僕はこういうのを読むと、自分ってちっぽけだなぁ。結局無力なんだなぁ。って思っちゃうタイプなんですけどね。
読書エフスキー3世 ま、私もそのタイプですけどね。だからこそ、アンナのような主人公に魅力を感じるんですよね。どんな世界でも前向きに、幸せを感じられる力強さに惹かれます。
書生 幸せを決めるのはいつも自分の心ですもんね。
読書エフスキー3世 相田みつをですか。そうですねぇ。確かに、世界がどんなに変貌しても、どれだけ犯罪が横行しても、自分はその中でも幸せを見つけられる人間でいたいですねぇ。
書生 いや、先生はロボやがな。
読書エフスキー3世 ゴゴゴゴゴ…
という事で、ポール・オースターの5番目の作品、『最後の物たちの国で』を読んでいきました。
ちょっと人を選ぶと思いますが、サクッと読める厚さの本なので、思い出したら手にとってみて下さいませ。
ここまでページを閉じずに読んで頂いて本当にありがとうございます!
最後にこの本の点数は…
スポンサードリンク
最後の物たちの国で - 感想・書評
最後の物たちの国で¥ 1100
- 読みやすさ - 87%87%
- 為になる - 79%79%
- 何度も読みたい - 89%89%
- 面白さ - 91%91%
- 心揺さぶる - 88%88%
読書感想文
ポール・オースターの他の作品とはまるで雰囲気が違う作品。相変わらず読みやすさの安定感は抜群。これからどうなるんだろうとページをめくらせる技術も素晴らしい。ラストの方は少しだけ心痛むシーンもあるけれど、読み終わった後は不思議な勇気をもらえる作品です。